神経症を治す〜神経症(不安障害)の治療方法
森田療法 個々の症状の心構えと対策
個々の症状とその対策
高良武久著作集・白揚社
完全欲は誰にもある。完全は気持よく、不完全は不快である。我々は我々のなすことが完全でありたいと欲するから、事をなすに当って、よく準備もし、よく注意もするのであって、完全欲がなければやりっぱなしになり、目的を遂げることが出来ないのであるから、完全欲そのものは、我々の生活上大切な心理であって決して病的のものではない。
 しかし完全とはいかなるものであろうかと詮索してみるとなかなかむづかしいことになる。ガラス窓を磨くにしても、どの程度によごれをなくしたらいいのかが問題になる。現在の気温では着物を何枚着たらいいか、ハンカチはどれくらい汚れたら洗っていいか、道を歩くにはどのくらいの速度がいいか、いちいち問題になってくる。そろばんを二度やっても安心が出来ず、三度も四度も繰返したり、戸締を二度も三度も調べなければ気がすまぬもの、手紙を書き封をしても何度も開いては調べる。ポストに入れても、よく入ったかいなか安心出来ずに幾度も手をつっこんでみる。
しかし完全とはいかなるものであろうかと詮索してみるとなかなかむづかしいことになる。ガラス窓を磨くにしても、どの程度によごれをなくしたらいいのかが問題になる。現在の気温では着物を何枚着たらいいか、ハンカチはどれくらい汚れたら洗っていいか、道を歩くにはどのくらいの速度がいいか、いちいち問題になってくる。そろばんを二度やっても安心が出来ず、三度も四度も繰返したり、戸締を二度も三度も調べなければ気がすまぬもの、手紙を書き封をしても何度も開いては調べる。ポストに入れても、よく入ったかいなか安心出来ずに幾度も手をつっこんでみる。
このように同じことを何度も繰返すことを馬鹿らしいと思いながら、心の不安があると、それを鎮めて安心したいために、気休めことをしているもので、不安をそのまま持ち耐えて行くことをしないのである。学生が夜、ガスストーブのガスの洩れるのを恐れて、夜中に五度も六度も起きては栓をしらべていたいというのも、ある主婦が着物を洗濯して物干にかけて、それが風のために落ちやしないかと心配になり、日に幾十度となく眺めて見るというのなども、どこまでも安心したい、不安をなくしたいという気分本位になり、事実にそくしない生活態度になっているのである。不安が起っても、一度確実なことを確めたなら、そのまままた不安が起っても、それをじっと持ち耐えてゆけば、恐怖を突破して新しい境地が開けるのである。もちろん一度や二度の突破ではない、毎日の生活でそれを実現していかなければならぬ。過失を恐れて、仕事が手につかぬというのも同様のことである。
我々は多くの事をすればする程、何か大なり小なりの過ちを起さぬわけにいかぬ。過ちを起して、それが将来のいましめにもなるのである。絶対に過ちを起してはならぬという態度になると、もはや何事も出来なくなる。何事もしないということは、これ程重大な過りはあるまい。神経質の人はそのことに気がつかぬのである。
我々が現実の事に多忙な生活を送る時には、その活動のリズムに乗って、いつまでも同じことにかかわってもおれず、時に応じことに臨んで自ら適するように精力が配分されて行くのであって、知らず識らずのうちに適当の判断も行われるのである。活動のリズムをつくることがまず大切のことであり、それは気分のいかんにかかわらず、気のついたことには即座に手を下していくという生活を馴致(くんち)しなければならぬ。間髪をいれずに手を下すのである。しかし、ただ不安を鎮めるための気休め事の実行はこれを厳に戒めることはもちろんである。
この発作は突然起ることが多く、時間は数分間のものが普通であるが、中には長時間に至るものもある。人によって程度の差はあるがこの際患者ははなはだしい不安に襲われ、今にも死ぬのではないか、心臓が止るのではないかという不安に襲われる。あるいは声を出して人を呼び、胸部を冷したり、医師を迎えて注射を要求したりする。かかる患者はまた、口内乾操、頭内充血感、四肢の冷感あるいは熱感、脱力感、身体諸部位の脈動感(どきどき波打つ感じ)、めまい、卒倒感、心臓部の疼痛感、呼吸促迫あるいは浅表感、耳鳴、咽喉の統狭感(しめられる感じ)、精神が錯乱しそうな感じ等の何れかをともなうことが多い。かかる場合の患者を見ると、顔色は蒼白で、呼吸は促迫(そくはく)し、脈拍は九〇以上一五〇に達するものもあるが、脈拍は一般に規則正しく、小さく軟かである。中には主観的苦痛に比して脈拍に大して変化のないものも多い。
一度びこの発作を経験すると、患者は、再度の発作襲来を恐れて、常に不安の状態がつづき不安な不吉な連想に悩まされ、誰もいない所で発作が起ったら、電車汽車の中で起ったら、歩行中に起ったらなどとそれからそれへと恐れて、ついに外出も困難になり、活動範囲は次第に狭められて、ついに我家より一歩も外に出られなくなる人もあり、中には臥床(がしょう)してしまうものもある。かかる人々はまた入浴を恐れることが多い。数ケ月間入浴せずにいる人もあり、浴槽に入っても不安のためただちに飛びでて、温浴を楽しむなど思いもよらぬという風になることが多い。これは入浴による体温上昇のために、心臓の拍動が盛んになることを恐怖するためである。また床屋に行くことを嫌う人も多い。これは、じっとして気を紛らすことがなく、不安に直面するので不安を強く感ずるためであろう。数回の発作を経験すると、もはや発作はほとんどなくなっていても、いつ起るかも知れぬという予期恐怖のために萎縮している人も多い。
本症が精神のからくりから起るということは、まず第一の発作の起った動機を見るとよく解るのである。例えば私の治療したある公吏は、スキーに出かけ、山中で吹雪に逢い、日も暮れかかったので非常な不安に襲われて突然動悸を覚えてから、心悸亢進発作(しんきこうしんほっさ)を持つようになり、ある青年は、中学生の頃友人が脚気衝心(かっけしょうしん)で亡くなったのを見て心臓麻痺を恐怖するようになってから心悸亢進発作が頻々(ひんぴん)と起り、ことに友人の毎月の命日になるとその不安がはなはだしく発作もはげしくなるという風になった。ある婦人は恐しい夢から醒めて胸のはげしい動悸を覚えてから、やはり時々心悸亢進を起すようになったのである。
一体我々の情緒と心臓のはたらきには密接な関係があるもので、昔の人は心が胸にある、ことに心臓にあると思っていた位で、心臓という言葉もそこから生れたわけであろう。胸苦しい、胸が痛む、胸騒ぎがするなどという言葉は、心の不安動揺と、胸部の器官、ことに心臓と密接不離の関係のあることを人が経験的に知っていることを示すものである。実験心理学的にも、情緒と心臓機能が互いに関連していることはすでに証明されていることで、どんなに些細な情緒の動きでもただちに脈拍に多かれ少なかれの変化を起すのである。生理学的にいうと、不安、苦悶、恐怖、吃驚(きっきょう)等の情緒の興奮は一般に交感神経の緊張を来たし、その結果、心臓の拍動数を増すということになるのである。
さて一度かかる発作を経験したものは、また起りはしないかという予期恐怖を持つようになり、ほとんど無意識的にも、不断に注意を発作に向けているという状態になる。それで何かの機会に前の恐ろしい発作の連想が浮び、はっとして胸の感じに異常を来すと、「来たな」という恐怖が卒然(そつぜん)として起り、俄(にわか)に心悸亢進がたかまってくる。しかし患者はこの発作の恐しさに夢中になっているので、自分の心のからくりには少しも注意が向いていないのである。だから当人は、精神的条件から起るものとは自覚せず、何か心臓の病気であると思い込み、ますます発作に対する不安を持つようになるわけである。 一言にして云えば心悸亢進発作は恐怖感動の現われである。恐怖不安の場合、植物神経の動乱が起りその結果心悸亢進の他に胸内圧迫感、眩暈(めまい)、脱力感、口内乾操、冷感、熱感等の起り得ることもまた当然である。
本症はいかに重症のものでも必ず治癒すべきもので、独力で突破し得ない人は入院療法で癒るものである。発作があっても決してこれに対して種々の手段を講ぜず、じっと耐えて己れの苦痛を見つめ、苦痛を迎える態度でいると間もなく消散する。いかに不安があっても身体的の仕事をつづけ、不安のために日常生活を制限しないことが大切である。発作があっても決して死ぬとかいうようなことはないものであるから、仕事をつづけてもなんら差支えないばかりでなく、苦痛に耐えて仕事をするという突破の生活でなければ治癒は望まれない。
我々がある仕事なり勉強なりをつづけているうちに必ず倦怠感を覚えるのは誰でも体験していることである。ところがこの倦怠は真の疲労とは必ずしも一致するものではない。興味ある仕事には倦怠感は容易に現われないが、嫌いなことにはただちに倦怠を覚える。好きな小説は夜遅くまで読みつづけて疲労しても倦怠感は中々起りにくいが、嫌な数学は一時間もつづけるともう倦(あ)きてくるという調子である。
神経質の人はこの倦怠感を疲労であると思い、自分は特別に疲労しやすくなっている。神経が衰弱している。身体のどこかに病気があるのではないかと危惧する。かかる人々は、仕事なり勉強なりに取りかかる前に、すでに疲労の予期恐怖があり、自分の不快気分に不安な注意を向けるのであるから、少しでも倦怠の気分があるとただちに疲労が来たと速断(そくだん)して、ますます自分の弱小感にとらわれるのである。ある一青年は、この疲労を恐れて四年間ほとんど何等の仕事もしなかったものであるが、三五日間の入院によって、疲労感のとらわれから完全に脱しているが、これは自分の神経が真に衰弱しているものでないことを、活動することによって体得しなければ容易に解るものではない。
能率減退感も同様である。一体我々の活動には必ず大小の波があり、律動を持っている。調子のいい時と悪い時が交互に来るものである。一日のうちにそれがあり、一時間のうちにもあり、細かく観察すると一分間の中にも緊張と弛緩の波があることは実験心理学的にも証明されることである。静かに時計の音を聞いていると、音が高くなったり低くなったりするのは、音そのものに高低があるのではなく、注意に緊張と弛緩のリズムがあるから、そう聞えるのである。クレーペリンの連続加算法というのをやると計算能率に不断の波のあることが明らかに現われる。
我々が嫌な仕事にかかる時は、初めどうしても気が乗らず仕事がはかどらないが、そのままに続けていくうちに、いつしか仕事に熱中して我を忘れているという風になり、つづけていくとまた倦怠を覚えてまた止めたくなる。普通人はかかることを当然のことと思い、あるいは当然とも何とも思わず、ただ気が乗れば乗るままに、乗らなければ我慢してやっているので、実際に少しも差支えないのである。しかるに神経質の完全よくの強い人は、常に今能率が上っているかいないかを問題にしているので、少しでも渋滞してくると、能率減退を悩み、そのために仕事の内容には一層身が入らずに、実際にも能率減退を来たすということになる。前にかかることを問題にしなかった頃は、万事すらすらといっていたように思い、それと比較して今は雲泥の差があるように思うのであるが、前にも時と場合によって能率の上り下りは普通人と同様にあったのであるが、患者はかかることには思いおよばないものである。また彼らは最も好調子の時を標準にして、それと現在を比較するので、大抵の時が駄目のように思われるのである。
不眠症の人は不眠ほど辛いものはないと思う。ただただ眠れさえすればよいと思う。眠れぬ夜を迎ええることは辛い。夕暮ともなれば、今日もまた眠れないのかと不安焦燥に馳られる。かかる人々には、安息の時であるべき夜が不倶戴天(ふぐたいてん)の敵のようになるのである。
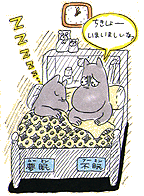 不眠はどうして起るか。
不眠はどうして起るか。
動機は人によって様々で一定しないが、心のからくりはすべて同様である。我々は何かの機会にふと眠れないことがある。心配事があるとか、何かに興奮したとか、あるいは夜コーヒーや茶を飲みすぎたとか、また身体の痛みがあるとか、また時には昼寝し過ぎたとかいうような場合、寝つきが悪いとか、途中で醒めて眠れなくなったりする。普通の人はこんなこともあるものだと思い捨てて、そのままにしておくので、たとえ一両日眠れぬことがあっても間もなくまた元に帰るのである。
しかるにある人は、不眠の害ということを重大に考え、不眠のために心身が衰弱するものと思いこみ、不眠を恐れ、眠ろう眠ろうと焦慮するので、その興奮のために寝つきはますます悪くなる。そうなるともう常に睡眠ということに注意が固着して、眠れたか眠れぬかを常に問題にするということになる。そうなると不眠を恐れるあまり、不眠の時間を実際以上に非常に長く感じてくる。うつらうつらの時間は丸で眠ったような感がしない。一体時間の経過の意識というものは主観的なもので、面白い遊びなどの時は瞬く間に過ぎ去るように感じ、反対に停留所に電車を待つような時は一〇分間でも非常に長く感ずる。身体の痛みのある時などはことに時間が長く感ぜられる。不眠恐怖の人が不眠の時間を長く感ずるのは当然のことである。これに反して熟睡の時間は無意識のうちに過ぎてしまうので、時間のうちに入らない。このようにして、不眠恐怖の人は実際は眠っていても眠ったように感じないのである。
なおここに注意しなければならないのは、不眠恐怖の人は出来るだけたくさん眠らなければならぬと欲張っているから、夜も早く就床し、朝も遅く起きて一日の臥床時間が一〇時間にもおよぶものがあるということである。いったい成人は普通六、七時間も眠れば充分で、時間が短ければ熟睡するから、正味五時間あれば実際は差支えないものである。我々は栄養に必要な量以上に食べていると同様に、多くは健康に必要な睡眠以上に眠りたがるものである。しかるに不眠恐怖の人が、一〇時間臥褥するとすれば、当然四、五時間は浅眠もしくは不眠の時間になるわけで、かかる時間は非常に長く感じられるから、ほとんど一晩中眠れなかったようにも感ずるのである。このように不眠恐怖の人は相当に寝ていても眠った感じがないのである。教室の掘田繁樹君はこのことを実験的に証明した。
不眠症の人々は、不眠の害を信じ込んでいるので、日常生活におけるあらゆる不快の心身の状態をすべて不眠のせいにしてしまう。昨夜眠りが足りなかったと思うと、もう今日は頭や身体の具合が悪いものときめているので、自己暗示的に症状をつくり出してくる。頭が重い身体がだるい、ふらふらする、疲労する、のぼせる、みな不眠のためだと思う。かくして不眠以外にもいろんな神経症状が生れてくる。
さてかかる不眠症に対していかに処置すべきであろうか。理解のよい機縁の熟した人は、本症の本態を知るのみで著しく軽快しあるいは全治する人もあり、一回の診療で数年来の不眠も一掃されることがある。病の性質を知るということは不眠症に限らず、すべての神経症に重要なことである。
次に実行すべきことは夜の臥褥(がじょく)時間を七から八時間に制限することである。これは始めのうちはちょっと困難なこともあり、不眠の翌日はいかにしても臥褥時間を長くしたいのであるが、それを押し切って実行することが大切である。就床時の心得としては、強いて眠ろうと努めることなく、眠れれば眠る、眠れなければ仕方がない。ただなり行きに任せておく、煩悶苦痛も起るままに任せておく、このことは強迫観念治療と同じことである。要するに眠る眠らないは仕方のないこととして、ただ就床しておればよい。昼間は夜の安眠不眠にかかわらず、また気分のいかんにかかわらず、作業に従事するのである。
かくして、睡眠のいかんにかかわらず、作業には差支えなきことを体験することが必要である。そうすると不眠が恐るべきことでないことがわかり、不眠恐怖も次第に消えて、自ら睡眠感が生じて来る。入院治療によって指導していくとほとんど例外なしに治癒するもので、当人も驚くほど経過の早い者があり、私の治療した婦人は「私が寝ている間に先生が魔法でも使ったものではないかと思った」と云う位に不思議に思っていたが、不思議でも何んでもなく、心境の変化によって誰でも癒るものである。ただこの心身の変化は眠ろうとする努力では決して実現するものではないということを注意しなければならぬ。
睡眠剤の服用は、かかる神経性の不眠には全く必要を認めないのみならず、かえって有害のことが多い。睡眠剤の服用が習慣性となり、その量が次第に増して、活動カをますます減殺させるのは我々のしばしば見るところであって、従来の物質療法偏重の弊害であると云わなければならぬ。
なお不眠を来す病気の一つに抑欝病というのがあり、これは一見神経質の不眠とよく似ているが専門的に見ると種々の点で異るものである。ここにその詳細を省くが、これには、時として服薬も必要な時があり、電撃療法を用いることもあり、神経質療法と趣を異にするのであるが、これも必ず治癒すべき性質のものである。本症患者は実際の不眠を有することが多いけれども電撃療法で速やかに治癒するものである。
音が気になって仕事も勉強も手につかないという人があり、一睡も出来ないと訴える人もある。かかるものを昔は神経が過敏になっているために、音を鋭く感ずるもののように考えていたが、これは神経の過敏とは別に関係のないことである。柱時計の音も耳についてうるさく感ずるという人が、電車に乗ってその轟音には何も苦痛を感じないところを見ても、雑音恐怖というものが心の構え方、心のからくりに関係するものであることがわかるのである。
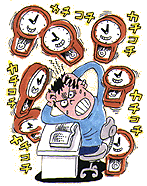 我々が何かあまり気乗りのしない仕事にたずさわるとき、次第に嫌気がさしてくると、物音に気がついて、仕事の方がちょっと留守になる。すると、仕事の運びの悪いのは音が邪魔するからだ、そのために注意が散乱し、精神の統一がとれないからだという風に解釈して、結局音を聞くまい聞くまいと念ずる。ところがその態度はもうすでに雑音と取り組んで争っていることになるので、ますます注意を音に向け、音はますます耳につきいらいらして来るという風に、精神交互作用が行われてくる。
我々が何かあまり気乗りのしない仕事にたずさわるとき、次第に嫌気がさしてくると、物音に気がついて、仕事の方がちょっと留守になる。すると、仕事の運びの悪いのは音が邪魔するからだ、そのために注意が散乱し、精神の統一がとれないからだという風に解釈して、結局音を聞くまい聞くまいと念ずる。ところがその態度はもうすでに雑音と取り組んで争っていることになるので、ますます注意を音に向け、音はますます耳につきいらいらして来るという風に、精神交互作用が行われてくる。
雑音もこれを排斥せずに聞き入れば、かえって刺激になり、作業能率を高めるという結果にもなる。静かな所ではかえって張り合がなくだらけてくる。私は大病院に勤務していた頃、医局員の大勢いる医局で盛んに論文もかき、著述もし、読書もした。医員の雑談や、野球のラジオ放送も少しも邪魔にならぬし、かえってそれが心を引き立てる役にも立つことを経験した。仕事に倦怠を覚えるとちょっと雑談の仲間入りもし、放送も聞いて楽しむ、そのまままた仕事に移り、いつのまにか、傍らの人声もラジオも全く耳に入ることを自覚しなくなるのである。私が高校時代不眠症に悩んだ頃、柱時計を外したり、隣室の人の話し声、歩く足音、衣擦れの音まで気になっていらいらしたときとは全く心構えが違っているのである。素直に受け入れて行けば、雑音も興味あるものとなる。
雑念恐怖の心理は、雑音恐怖となんら異なるところはない。
一体世の中に雑念の湧かない人があろうか。我々の身体器官は常に働こう働こうとしているものである。それゆえに眼が開いておれば、何かを見ないわけにはいかぬ。同様に醒めておれば脳が常に何かを感じ、何かを考えないわけにはいかぬのである。文字通りの無念無想というものは深い麻酔に陥っている時、昏酔時熟睡時以外にはないのである。こういうと雑念恐怖の人は必要なだけを考えるのならいいが、不必要な何もならぬことに考えがうつるのは困るという。はなはだ勝手な云い分であるが、迷っているとその得手勝手の程もわからぬ。
今私が時間を調べようとして机上の置時計を見るとすると時計の文字盤の外にその装飾や、傍のインキ壷、マッチ等が眼に入る。時を見るのにこれらのものは不必要なものであるが、矢張り見ないわけにはゆかぬ。強いて見まいとすれば、時計の針まで見ないようにするより他ない。我々はかかる場合、時計と共に他のものが見えるのは当然のこととして少しも怪しむことなく、素直に受け入れているから、それが少しも邪魔にならず、見えるということすら意識しない位である。同様に我々がある仕事をし、ある問題を考えようとするとき、それに関連した必要のことだけが頭に浮ぶということはほとんどないのである。
連想は様々の方面に起って、当面の必要事項と一見関係のなさそうなことまで浮び上ってくる。それが普通のことで、常態である。様々の連想の中から、当面の問題に役立つものを採択し、総合して、そこに有用な思考が成り立つのであるが、大抵の場合採択しているという意識もなく、目的にかなうように撰択は行われている。机上のペンを取ろうとする時、他のインキやノートが見えても一向邪魔にならずに、手は自らペンの方に向いて行くようなものである。
しかるに雑念恐怖の人は、当面の必要以外のことが頭に浮んでくると、これを雑念と名ずけて、それを抑えようとし、雑念と格闘しているのである。当然あるべき心理を否定し排斥しようとする努力は、不可能を可能にしようとするものであるから、葛藤はますますはげしくなり、肝心の仕事の方は留守になってしまうという結果になる。
雑念恐怖の人は「自分はこの病気になるまでは雑念はなかった」というけれども、それは認識不足のはなはだしいもので、以前にも決して雑念がなかったのではない。ただ前にはそれを当然のこととして素直に受け入れていたに過ぎない。対人恐怖の人が、以前はそれがなかったというのと同様である。人間としてあるべき人情や心理は病気であろうがなかろうが、誰にもあらざるを得ない。それを仕事の妨害になると考えて、雑念を排斥しょうとして、初めて雑念が意識の全面に立ちふさがって、実際にそれが仕事の邪魔になって来たのである。
完全欲の強い神経質者は勉学するにも、完全な精神統一の状態でなければならぬと念ずるので、事実に裏切られて、かえって雑念のとりこになってしもう。精神の統一も何もいらぬ。雑念があるままに、雑念もどしどし起しながら、それに逆らわずに仕事もやり、勉強もする。そのうちに雑念も決して邪魔になるものでなく、雑念の中に趣味もあり、重要な思考もその中にひらめくことを悟るであろう。雑念という名前をつけるから、排斥したくもなる。我々が珍重する高山植物も、高山においては雑草に過ぎないのだ。雑念を排斥すれば、貴重な思考も共に捨て去るということになる。
7・振顫(しんとう)と職業性痙攣(けいれん)、特に書痙(しょけい)
神経系統の器質的障碍(しょうがい)のある病気で身体のある部分に振顫を来すことがある。しかしかかる器質的の病原よりも、精神的からくりから起るとおころの神経質症状としての振顫の方がはるかに多い。この精神的条件から起る振顫は、ある特定の場合、特別にふるえるというのが特徴で、これが器質的の病気と異なるところである。例えば人前に出て何かする時に身体全体がふるえる。手足がふるえるとか、人前で酒杯や茶碗を手にしているとき、そろばんをするとき、字を書くとき手がふるえるもので、人前でやるときことにはなはだしく、自分独りの時はさほどでないという特徴を持っている。もっとも書痙などひどくなると、独りで自室にいるときにも相当にふるえるが、人前に出ると一層はげしくなるものである。
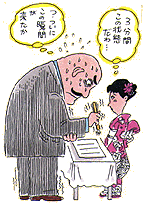 かかる振顫の起る動機は各人各様で、自分では自覚しない人も多い。課長の面前で字を書くときふるえるのに気ずいて、それ以来書痙になった人もあり、ある中年の紳士は、友人と酒席にあって、芸妓に酒をつがれたとき、手がふるえたのを友人に冷かされて以来、人前で盃を手に取るとふるえて酒がこぼれるようになり、宴会に出るのが非常に苦痛になった。ある局長は部下に訓辞を与えるとき、腰がふるえるのを自覚してから、人に面接しているとき身体がふるえだして、安楽椅子にしっかりつかまるのが習性になった。
かかる振顫の起る動機は各人各様で、自分では自覚しない人も多い。課長の面前で字を書くときふるえるのに気ずいて、それ以来書痙になった人もあり、ある中年の紳士は、友人と酒席にあって、芸妓に酒をつがれたとき、手がふるえたのを友人に冷かされて以来、人前で盃を手に取るとふるえて酒がこぼれるようになり、宴会に出るのが非常に苦痛になった。ある局長は部下に訓辞を与えるとき、腰がふるえるのを自覚してから、人に面接しているとき身体がふるえだして、安楽椅子にしっかりつかまるのが習性になった。
かかる振顫は自分の職業に関係していることが多く、会社などで文字を書く職務の人が書痙を起し、お茶の先生が茶碗を持つときふるえるとか、音楽の教師がヴァイオリンを弾くときにふるえるとか、会計の人がそろばんをするときにふるえるとかいう具合になるので、職業性痙攣(けいれん)という名前がついているのである。昔は(今でもそう信じている医師もあるが)その筋肉をよけい使うので、神経の変調を来すと考えられたりしたが、いくら休んでも癒るものではなく、マッサージや、電気療法などやってもなんら効果はないもので、そこの神経の過労とは何も直接の関係はないのである。
文字を書くとき、ふるえたり、ひきつるようになったりして思うように書けないのを書痙といって、これは随分多いものである。学者は書痙を、痙攣型、振顫型、麻痺型等と種々分類しているが、実際にはこう判然と区別出来ないものが多く、また治療上にも型のいかんはさして意味を持つものではない。同一人において種々の趣が混じているものが多い。
人前で起る振顫や職業性痙攣が、神経質の一分症に過ぎぬことを発見したのは故森田正馬博士の功績であり、本症は精神的条件から起り、神経質療法で治癒することが明かになったのである。
発病の原因は他の神経質症状と全く同様のもので、ある機会に人前でふるえたりすることを自覚すると、それが非常な醜態であると感じ、あるいは自分の職業上の非常な痛手であると感じ、次の機会には予期恐怖にとらわれて異常に緊張し、自己暗示的にますます振顫を発し、さらにふるえまいと努力してますます緊張する結果、ふるえはますます増大してついに固定的症状を形成するのである。この症状を克服しあるいは逃げようとして、細工をろうする程ますます不快、嫌悪、恐怖の情は増し、日常生活にも支障を来たすようになる。
本症に対する心構えとしては一般治療の心得を守り、単に局部的症状を癒すことに専念せず生活全体の向上発展をうながさなければならぬ。症状そのものに対しては、振顫失調等は、今は仕方のないものとして、そのままに拮抗することなく、むしろ進んで顫えるという位の気持で、やるべきことをやる。顫えさせないためにいろんな手段を試みることは有害無益である。ことに書痙の人などは、ふるえさせまいとして、ペンや筆の持ち方まで変え、紙のおき方、姿勢などさまざまに変えているものが多いが、かかる手段は一切止めねばならぬ。すべて普通の健康人がやるように書くことが大切である。また達筆で書こうとせず、誰にもわかりやすいように、楷書できちんと書くようにするがいい。本症は大体対人恐怖と同様の性質のものであるから、その方のことも参照すべきである。根本的に神経質療法を行えば、局所の症状にはほとんど触れずに、いつのまにか全治するものである。
病気にかかることを恐れる、あるいは現在持つ病気をいたむ心は、程度の差こそあれ万人共通のことであろう。自己保存欲の欠乏する精神病者、白痴、極端な変人は例外である。衛生思想が発達するにつれてその一面の弊害として恐怖症患者も増加してきた。
ヒルティは「多くの人にあっては、健康保持の関心が、まさにあらゆる他の関心を凌駕する程である。世界歴史において、幾千の虚弱病弱の人が、それにもかかわらず、否、かえってそのために最大の事業をなし、よく苦難に堪えたことを彼らは全く忘れているように見える」と云っているが、現代のある人々にはまことに適切な忠告である。
世には「衛生思想の漫画」を思わせるような恐怖症患者が多く、普通人から見るとむしろ滑稽にも見える程であるが、当人の身になると身をけずるような思いで、莫大な金と時を費して苦悩をつづけているのである。
恐怖の対象となるものは、肺結核、精神病、性病、心臓病、高血圧、癩(らい)病る生理的感覚を病的のものであるとして、これを恐怖するもの、また局部に不安な病意を集中して起る異状感覚を病的のものとして恐れるものもある。また局部より悪臭を発して他人に非常な迷惑をおよぼすものと誤信しているものがあり、また自己の自汚行為が他人に看破されていると悩むものもある。また何かの機会(飲酒、精神的恐怖)に偶然性交不能を経験するとそれが深刻な恐怖となり、次の機会には予期恐怖のため萎縮して性交不能となり、愈々(ゆゆ)それを恐怖して陰萎ということを不断の問題にする。早期射精すなわち早漏等もやはり神経質者の完全欲から、自他の完全なる満足を期待して焦慮し、あまりに完成を急ぐとこから生ずるものである。なおこの症状を訴えるものは多くは独身者で、正しい結婚生活における場合のごとき落ちつきを欠くことも重要な理由になるもので、かかる者も結婚後は普通の状態になることが多い。
皮膚泌尿科においては、性に関する神経質症状の多いことは前述の如くであるが、かかる患者の多くは泌尿科の医師を訪れるとき、実際自分に器質的疾患があるものと相当に信じていて、医師もしばしば患者の言葉につられて、ついありもしない病気を治療するという結果にもなるのである。
性に関する症状は種々であるが、訴えの種類を挙げると次の通りである。是等の症状は勿論すべて精神的条件が主になって起るもので、患者が信ずるように局部に本質的病変があるわけではない。
患者は勃起後に摂護腺の分泌液が多少でもあると、これを精液の満失であると恐れたり、又遺精、夢精を極度に恐れ、それがために心神が消耗疲労するものと信ずる。或は睾丸陰茎等を押して感ずる生理的感覚を病的のものであるとして、これを恐怖するもの、又局部に不安な病意を集中して起る異状感覚を病的のものとして恐れるものもある。又局部より悪臭を発して他人に非常な迷惑を及ぼすものと誤信しているものがあり、又自己の自汚行為が他人に看破されていると悩むものもある。又何かの機会(飲酒、精神的恐怖)に偶然性交不能を経験するとそれが深刻な恐怖となり、次の機会には予期恐怖のため萎縮して性交不能となり、愈々それを恐怖して陰萎ということを不断の問題にする。早期射精即ち早漏等も矢張り神経質者の完全慾から、自他の完全なる満足を期待して焦慮し、余りに完成を急ぐとこから生ずるものである。なおこの症状を訴えるものは多くは独身者で、正しい結婚生活における場合の如き落ちつきを欠くことも重要な理由になるもので、かかる者も結婚後は普通の状態になることが多い。
更に数多く見られるのは性器の発育不全を苦にするもので、自己の性器の短少なることを悩むものである。我々がかかる患者の性器を診ると、すべて普通生理的範囲内にあるもので、特別発育の悪いものは決してなく、その機能にも何等障碍はないのである。当人は過去における自とくによって発育が妨げられたと思い込んでいるのが多い。一体陰茎の大小は、その時の欝血の如何による事が多いのである。患者は入浴の際他人の性器を見て自己のそれよりも大であると思うのであるが、入浴時においては陰茎及び尿道の海綿体の欝血があるから、平時よりも大きくなっているのである。然るに患者は自己の性器が短少であるとして、これを人に見らるることを恐怖するから、その精神的作用によって陰茎は当然萎縮しているのである。他人の欝血せるものと自己の萎縮せるものを比較して患者は頻りにこれを欺くのである。彼等は自己の性器短少を恰も男性らしからざることの象微のように思う。
次に自とく恐怖であるが、ある程度に自とく恐怖を持たない青年は無いと云ってもよく、それあるがために過度に亘ることも避けられるわけであるが、その恐怖に捉われて、自ら神経衰弱状態に陥るものは、神経質症状としてこれを治療しなければならぬ。一体自とく行為は独身青年に普通の事で、それ自身何等病的の事ではなく、生理的のことである。然るに世には自とくの害を過大に書き立てる通俗医学者や広告があって、神経衰弱が自とくに基くものであり、精神病の原因にもなるものであるという謬った見解が行われて、これが患者の恐怖を駆り立てるのである。自とくの経験の無い者は少ないので、それらを読むと、成程そうかと思い当るのである。
しかし自とくはむしろ生理的行為に属し、思春期における一週一、二回の自とくは特に有害であるとは認められない。患者は、他の種々の症状を自とく行為と結合して、すべて自とくの害に基くものと考えるのであるが、実は全く因果の関係は無いのである。遺精、夢精等もすべて同様の事で、何等有害のものではない。世には精液の一滴は血液の何十瓦に相当するものであるという愚にもつかぬ説が行われたりして益々患者を迷いの中に追い込んでいる。心すべきことである。なお自とくが心身に悪影響を及ばしていることを恐怖するものの他に、自己の自とく行為が他人に看破されているのではないかということを恐怖するというものもある。
その他変体性欲恐怖等、性に関する神経症状は種々あるが、ここには省略する。
さてかかる症状を持っているものは、殆んどすべての場合、其他の精神的随伴症状を持っている。即ち不眠、心悸亢進、疲労感、対人恐怖、小心、取越苦労、頭内朦朧感等の何れかを伴っているもので、患者はかかる症状が性器短小、自とく、遺精等々のために引き起されるものと憶測するので、愈々主訴の事を問題にするのである。すべてかかる性に関する症状或は随伴的の神経症状は、何人にもある機会に起り得る生理的の事に過ぎないのであるが、不安な自己反省に傾き易い神経質的性格者は、これをすべて自分に特別な病的の事ときめ、精神的からくりに依って自ら症状を重くしているのである。それ故に医師はこれを治療するに当って、かかる症状の成り立つ心のからくりを説明し、症状の本態を自覚せしめることが必要である。患者の中にはそれを明らかに理解したばかりで治癒するものもあるが、それは機縁の熟した者であって、中には文字の上で理解しても容易に治癒しがたいものがあり、かかる者は、体験療法に依って神経質全体の陶冶をはからなければならぬ。
しかし医師がこの症状の本態を熟知せず、例えば神経質の陰萎、性器短小感、遣精等を器質的疾患として、これに性ホルモン等の注射等を施す時は、時には一時的に多少の暗示的効果を見ることはあっても、決して永続的効果を望み得ないのである。我々の所を訪れるかかる患者の多くは数十回或は一〇〇回に及ぶホルモン注射を施行されても効果を見なかったものが多いのであり、この点大いに医師に警告したい所であり、医師は症状の成り立ちを知り、之が神経質症状に他ならぬことを洞察し得た場合、直ちに局部的の治療方針を一擲し、神経質全体を治療することを眼目とし、これに合理的な精神療法を施さなければならぬ。
10・対人恐怖(赤面恐怖、正視恐怖、自己表情恐怖、多衆恐怖等)
神経質症状のうち、疾病恐怖と対人恐怖は最も多いものでまず横綱格である。
一体対人恐怖を少しも持たぬ人は極めて稀なもので、そんな人はむしろ少し変った人であるといってもいい位のものである。普通人は多かれ少かれある程度の対人恐怖を起すのは当然のこととして別に不思議とも思わずに暮して行くのである。
古人が人は社会的動物であると云ったように、人間は孤立して存在し得るものではない。孤島のロビンソン・クルーソーも人間がいなければ犬や鸚鵡(オーム)を友とするが、やはり人間が恋しくてしかたがない。精神分裂患者の多くは、はなはだしく人間が嫌いで、出来るだけ人を避け、人との交渉をなくして自分独りの得体の知れない生活をするのであるが、これは特別なもので、すでに人間的感情を喪失したものである。
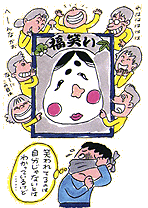 神経質の対人恐怖の人々は、やはり人を避けたがる。しかし決して人と離れたままで満足しているのではなく、人と親しみたい、人に好かれたい、尊敬されたいという欲望を充分に持っているのであるが、対人恐怖という強迫観念のためにそれが出来ないことを悩むのである。分裂病の人には病気のために始めから人と交りたいという欲望がないのであるから、厭人症があっても、その症状のあることを苦にしないので、神経質の強迫観念とは全く異なるものである。
神経質の対人恐怖の人々は、やはり人を避けたがる。しかし決して人と離れたままで満足しているのではなく、人と親しみたい、人に好かれたい、尊敬されたいという欲望を充分に持っているのであるが、対人恐怖という強迫観念のためにそれが出来ないことを悩むのである。分裂病の人には病気のために始めから人と交りたいという欲望がないのであるから、厭人症があっても、その症状のあることを苦にしないので、神経質の強迫観念とは全く異なるものである。
さて神経質の対人恐怖症にもいろいろ個人的の趣きがあって一様に述べ難いが、最も多いものを述べて見よう。
(1)赤面恐怖人前で赤くなること、顔のほてる感じが、人に注目されるようで非常に恥ずかしく、そのために人前に出ることを嫌がるものである。こんな人は人から血色が好いと云われても、自分の赤面を指摘されたようで、はなはだしい不快を感じたりする。そのために種々の小細工もやったりするもので、非常に暑いという恰好をして、顔の赤いのも暑さのためだと人に思わせるようにしたり、何度も冷水で顔を洗ったり、酒でごまかしたりする。まるで赤面地獄に堕ちたょうに悩むものである。ところが中には格別顔は赤くならないで、ただ自分でほてる感じがするので、赤くなるものときめこんでいる人もある。
(2)正視恐怖人と面と向っているとき、視線のやり場に困って非常に狼狽する。その不快を嫌がって人前に出るのを避けるのである。これではならぬと、相手を見つめると苦痛はますますはげしくなってくる。
(3)自己表情恐怖仮にそういう名称をつけたのであるが、人によって様々である。自分の顔が醜いときめこんで、人前に出られない、人に失礼になるというもの、人に対するとき顔がこわばるとか、笑う時も泣くようになるとか、唇の曲り方が変であるとか、ことに多いのは眼に関するもので、自分の眼つきが鋭くて人に不快をあたえる。白眼が多過ぎる。肩がどうであるとか、自分の顔に種々の難癖をつけて、人前に出られないと欺くのである。そのために、眼鏡を種々取り代えてはかけて見たり、眼科医の所に行って手術を受けようとしたりするものもある。また自分の眼に力がないということで、人から軽蔑されると思い込む人もある。
また顔だけに限らず、物事をするのに自分の手つきが変である。歩く時の恰好が変であるとか、あるいは自分の体臭が人に不快を与えるとかを気にするというのもある。腋臭があると思い込み、また事実多少あるのを非常に重大視して、毎月シャツを洗ったりしなければ人前に出ようとしないものなどもある。
対人恐怖にも種々あって、個人に対しては格別のことはなくても、多人数の前に出るのが極端に嫌なもの、あるいは個人的対談に際して、話すべき話題のないことが苦になるもの、人に対するとき堅くなり、ぎこちなくなるのを嫌がるもの、ふるえるのを恐怖するもの種々様々である。
先にも述べたように我々の本心は、人に好かれたい、人に親しみたい、人に重んぜられたいというところにある。その方が生存上都合がいいからである。そういう心が一方にあると、必ず一方には人に不快をあたえることはあるまいか、嫌われはすまいか、軽蔑されはすまいか、という不安があるのは当然である。ことに長上の人々や多人数の前、男性に対する時など、自分がよく思われたい欲望が強いから、一方には悪く思われはしないかという不安も一層強いわけで、それが人情の自然である。その自然にまかして、恥ずかしいままに、恐ろしいままに、嫌なままにそういうものと心得て、人に好かれたい本心に乗って人に接して行くのが普通人であって普通の人は対人恐怖心をなくしようともしないから、対人恐怖が格別問題にならないのである。しかるに神経質の人は、その人前における苦痛、羞恥の感じなどを嫌がり、かかる感じをなくそうとして、不可能の闘いをするので、強迫観念化して、対人的苦痛恐怖が二重にも三重にもなっていくのである。
花を見れば美しいもの、毛虫は気味悪いものと、ありのままに受け入れていく時強迫観念は起りようがない。人の前に出て心の動揺があるからこそ、人と調和していけるので、あたかも遊動円木(ゆうどうえんぼく)に乗って、円木と身体が共に揺れて調和が保たれるようなものである。
対人恐怖の人は苦しいままに、恐しいままに、恥ずかしいままに、仕方なく人に接していかなければならぬ。苦しみを避け、人から逃げてばかりいてはいつまでもらちが明かぬのである。
人情の必然的心理から逃げようとしても、それを否定しても、成功しないばかりでなく、ますます葛藤が増すばかりである。正視恐怖の場合などを考えると、いかに神経質的とらわれから、人情の自然に逆らっているかがわかるのである。彼らは、人と視線を合わしたとき、誰でもパッと眼をそらすのが自然であるという簡単な事実にさえ想いいたらない。我々は人と話をしているとき、視線は一点に固着させていない。あるいは相手の全体、もしくは顔を漠然と見ていることもあり、あるいは胸のあたりに移ったり、方々にさ迷うのが普通のことである。相手が自分の眼を見ていないときは、その眼を見入ることも出来るが、向うの視線と自分のが蓬うと、バツが悪くなって、瞬間に眼を外らすのである。もし視線を合わせたまま対しているならば、それは憤怒の場合であるとか、あるいは異常の精神状態においてである。酔漢の目がすわるという時、または、狂人の眼は相手の眼を凝視するのでまことに気味の悪いものである。普通人は誰でも視線を合わせている時のバツの悪さに耐えられない。しかるに神経質の人は、眼を外らすのは負けである、意気地がないからであると思って、強いて見ようとすると、自然の心理に従って妙な嫌な気持ちになる。凝視しょうとすればする程苦しくなり、ついに人の顔を仰ぎ見ることも出来なくなる。それで色眼鏡をかけたりするものである。人情の自然に反抗するところに葛藤が起るのである。
対人恐怖の人は他人と自分を対立的に見ればいつも人と自分を比較して、自分が人より弱い意気地なしと思い、人の前に出ても引目を感じないように心の平静を失わないように、人に負けないようにと念じて、自然の人情である対人的感情の動きをも否定しようとする。そこに強迫観念のなり立つからくりがあるのであるから、まず何よりも人間の自然の心理に従順になることが大切である。人に勝とう勝とうとせず、下手に出て、人に好かれるように心がけ、話し上手になろうとするより、聞き上手になろうとするがいい。人に対してはびくびくはらはらのまま、なるたけ笑顔で接するがいい。彼らは人に負けまい、動揺してはいけないと、不自然に頑張るので、かえって傲慢にも見え、そうなると、人からも嫌がれる傾きがある。人が先に礼をしないと自分も頭を下げないという調子になりやすい。真の親しさがないのに笑顔で接するなど、おべっかが出来るものかと、自分本位の狭い量見でますます世の中を狭くしているのである。私は対人恐怖では青年時代長い間苦しんだことがあるので、かかる人々に対しては特に同情のあまり辛辣なこともいうのであるが、私の言葉を率直に受け入れてゆけば、癒るに従ってその真意がわかる筈である。とかく、神経質の人には理屈が多い。中にも、対人恐怖の人は格別理屈に流れる傾きがある。迷いの中の理屈は是非共に非なりで、迷っている間の理屈は気分本位の独断に陥りやすいものであるということを戒心しなければならぬ。
なお、対人恐怖のひどい人は、人が話をしていても自分のことを云っているように思ったり、人が笑っても自分を冷笑しているのではないかと悩むという調子になる。こういうのを関係念慮といって、自分の気持で、自分に関係のないことを関係があるように感ずるものである。そしてその誤りが自覚されにくいこともあるが、癒るに従って自分の思い過しであることがわかるものである。
頭が始終重い、蓋をかぶっているようだとか、びんと糊で張りつけたようであるとか、頭の中に何か入っているような感じがするとか、頭が痛む、頭がぼんやりして、物事をぴったり感ずることが出来ない。ぐらぐらと眩暈がして今にも倒れそうな気分になる。始終耳鳴りがする、或は自分が自分でないような感じがする。周囲と自分が何となく離れ離れになっているような感じがする。肩が凝ったり、右と左の身体の感じが違っているような感じ、胸がつまっているような感じ、其他種々雑多の症状がある。
かかる神経質症状はすべて注意の捉われ、自己暗示、精神交互作用等に依って発生するものでここに一々説明する程の事もない。
頭のぼんやりしている感じも神経質の人に多い症状であるが、これも外界の事に注意が向かないで、頭の感じに捉われていることから起るのである。一体我々の精神というものは、外界との接触に依って鋭敏に働くもので、外界との接触がなくなると自然にポーとして眠くなるという具合である。私は頭をぼんやりさせようと思えばいつでも出来る。それは、外界の事に注意を向けずに、自分の頭の状態を感じていると直ぐにそうなるのである。神経質の内向的気分において、頭内朦朧感が起るのは当然のことである。
その他外界がぴったりしない感じ、自分が自分でない感じなども矢張り同じ様なことで、誰でも、自分の状態や感じを細かく観察する人なら、ある機会に経験し得ることである。神経質の人はそれに捉われて、症状化しているに過ぎない。
治療の方針は、他の症状におけると同様である。異常感覚があるままに、健康人と同様の忙がしい生活をしなければならぬ。
神経質症状を有するほとんどすべての人に共通のことであるが、特に対人恐怖を持つ人には例外なしに劣等感が強いものである。何事につけても自分が人より劣っているように思う。人のように気がきかない、間が抜けている、理解力も、記憶力も、実行力も、何もかも劣っているように思われる。何事にも引け目を感じて、自分の顔や身体までみすぼらしいもののように思う。そうなるとますます引込思案になり、積極的行動を取らなくなるので、実際人並のこともしなくなって、人より劣っているという状態になってしまう。
ところが、かかる人々を我々が指導して種々なことをやらせると、実際は決して人より劣っているのではなく、真の劣等ではないことがわかる。彼らは完全欲が強いので、少しでもまずいところがあると、そればかりを問題にしてとらわれるのである。とらわれると自分の真の能力を正しく見ることが出来ない。メンタルテスト等やって能力が決して劣っていないことを証明しても、なかなか承知しないもので、まぐれ当りだとかいって、強情に自分の力を信じまいとするように見える。
本来劣等なものは己れの劣等を気にしないもので、真の低能者が己れの低能を悩まぬのと同様である。己れの劣等を欺く人は、真の劣等ではなく、完全欲の現われに過ぎないのである。生の慾望が強いから死の恐怖があるというようなものである。
劣等感に悩む人は、例えば鋸引(のこび)きをするにしても人よりうまくやれないという。ところが鋸引きを始めからうまくやれる人は少ないもので、彼らはすでに前から幾度もやっている人と自分を比較して自分がまずいと思うのであり、自分が練習していないことに少しも想い到らぬのである。また他人の苦悩は自分にはわからぬもので、他人は人前で楽に物をいう、楽に勉強し、仕事をしているように思う。そして自分だけが何事もすらすらとやれないものと独断しているのである。劣等感のとらわれは、自分が努力して大抵のことはやれるということを体験しなければ癒りにくい、苦しいから、劣るからといって慣れないうちに中止するようではいつまでも脱却することは出来ない。劣等感の人は食わず嫌いの人が多いのである。始めから出来ないものとして手を出さぬようでは、真の劣等者と同列におかれても仕方はないのである。
癒れば、劣等感があるということが、我々の努力、活動性を刺激して、精進の生活への拍車になることが理解されるのである。
従来胃アトニーとして種々の食養生や服薬をつづけて全治しないものの大部分は本症である。食物が長く胃部にもたれる。張るような感じがする。嘔気を催すもの、痛みを感ずるもの、腹鳴がするなど種々の症状があり、あるいは長く便秘に傾くもの、下痢しやすいものもある。レントゲン写真を撮って見ると、胃の下垂したものもあり、そうでないものもある。事実下垂していても、神経質療法を施せば、なんら実際にはさしつかえないものである。かかる人々は食物に関して非常に過敏になり、消化不良と思われるものを避け、粥食のみをつづけるのもあり、次第に食も減じていく。初めは三杯で満腹感が出来たものが二杯ですでに満腹の感じがで、さらに一杯でももう腹が張ったようになるという風になる。こんな調子で彼らの多くは痩せて、無力性体質が一層目立って来るし、充分に食を摂らず、運動もあまりしないので、胃も実際廃用性萎縮のようになるのである。
かかる人々に対して我々はその衛生の亡者振りを是正し、普通食を摂らせ、仕事も盛んにして筋肉も発達するように仕向けるのである。根本は疾病恐怖であるから、我々の治療でこれを陶冶すれば自ら治癒するのである。私の治療した青年は十数年来の下痢と便秘等のために体重約39キログラムになっていたものが、三カ月経たぬうちに52.5キログラムを突破しているのである。またある老学者は二〇年来毎日下剤を服用しなければ便通がなかったのであるが、入院中これを完全に突破してしまったのである。とらわれるということは、ただ精神的のことのみに止まらず、身体的にも非常に影響をおよぼすもので、ことに消化器、心臓血管等には著しい変化をもたらすものである。しかしそれは機能的のもので、別に器質的のものではないから、放置しても生命に危険はないし、相当の鍛錬にもよく耐えられるばかりでなく、鍛錬によって始めて治癒すべきものである。しかし相当重症になると症状がはなはだしく起るので、それに負けて、独力で突破出来にくいもののあることは遺憾である。
ある婦人が私のところに来てこういうことを訴えた。「万年青(おもと=ユリ科)」という観念が、頭に浮び上って、他のことはまるで考えられない、どんなにこの万年青の観念が浮び上るのを防ごうとしても、どうしても止めることが出来ない。目の覚めている間は万年青のことで心が占領されているというのである。ただこれだけのことでは不思議にも思われるのであるが、その起り方を見ると他の対人恐怖や疾病恐怖と本質的には変りはないのである。この婦人は家庭のことで、不安な境遇にあったとき、知人が訪れた際、その人に万年青のことについて、その栽培法や何かを種々話したのであるが、話がすんでから、自分が大してよく知りもしないことをおしゃべりしたが、その中にはでたらめのこともあったように思われて、非常に恥ずかしい気がした。その後万年青のことを想い出すと嫌な気分になるので、万年青のことを考えなければよいのだということに気づき、その考えが浮ぶと、しきりにそれを抑えつけようとしたのである。つまり不快な気分が嫌だからそれをなくするために、万年青を考えまい考えまいと念じたのである。ところが実際問題としては、そういう事件があれば、誰でも、万年青のことを考えると連想がすぐその事件と結びついて不快になるのは当然なわけである。普通の人はそのままそんなものと心得て思い捨てるのであるが、少しの不快をもなくすことが出来ず、強いてその観念を排斥するので、逆作用でかえってその観念に取りつかれてしまうのである。流れを渡るとき、流れにしたがって斜に行けばよいものを、流れにさからって行くので抵抗を強く感ずるようなものである。
私は強迫観念を次のように定義したことがある。「強迫観念とは、ある機会に普通人にも起り得る心理的または生理的事実を、ヒポコンドリー性気分より、何か病的のこと、異常のこと、あるいは自己保存上不利のこととして不安に感じ、この不安を来す事情あるいは不安そのものを排除しあるいはそれより逃れんとして成功せざる心の葛藤、およびそれに付随する苦悩煩悶の全過程を意味するものである」と、何だかむずかしいようであるが、実際にあてはめて見ると容易に理解されることである。
こんなわけで、強迫観念の内容は、その人の経験したことによって、無数にあるわけで、ここでいちいち述べることも出来ないくらいであるが、比較的頻繁に見られるものを簡単にここに述べて見よう。
不潔恐怖
これは黴菌(ばいきん)恐怖や伝染病恐怖と一緒になっていることが多い。いたる所に不潔物があるような気がして直接物に触れることが困難になり、触れた後ではすぐ手を洗うとか、リゾールやアルコールで消毒しないと気がすまないという風になると、日常生活も非常に困難になる。一日に二〇度も手を洗う人もある。あるいは便所に行っても数十枚の紙を費すとか、着物を着たままでいけないというのもあり、あるいは一日の大部分を掃除に費す例もある。私の治療した一人の婦人は、洗濯した自分の着物に一寸でも他人の手が触れると、必ずそれをもう一度洗い直さなければならず、洗った着物を入れてある箪笥(たんす)を他人が一寸でもあけると、非常に不安になって、それを全部洗い直さなければならぬというのがあった。
罪悪恐怖
自分が何か悪いこと、不正のことをやりはせぬかということが気になる。人中に出てひょつと人の物を盗りはしないか、猥褻(わいせつ)なことをやりはせぬか、ふっと乱暴を働きはしないか、人の頭をなぐることがありはしないかなどと恐れて、人中に出ることも困難になる。マッチでも持っていると、ふとした衝動で放火するようなことがありはしないかなどと恐れて、火気に近づくことも出来ないというのもある。以前は式場に出て御真影(天皇、皇后の写真の敬語)に対し何か不敬なことを口走りはしないかというようなことが不安で、式場に出られないということもあった。
不正なこと危険なことを実行しやしないかと恐れるばかりでなく、悪い考えの浮ぶのを恐れるものも多い。実行しないことはちゃんとわかっている積りでも、悪い考えの起ることが辛いのであり、起すまいとする程しつこく変な考えが浮び上ってくる。神社、仏閣、式場等において不敬な考えが浮ぶので非常に恐れるというのも多いもので、涜神(神を汚すこと)恐怖と命名されている。神社や寺の前を通ることも出来なくなるのがある。また人に対していろんな口に云えない猥褻な考えが湧き、失礼なことを起してはいけぬと思う程、ますます突飛な性的なことがひよいひよいと頭に浮かんで、そのために疲労困憊(こんぱい)するのもある。また高い所にいる時など自分の子供を突然つきとばすことはないか、今にもそんなことをしそうな気がして不安になるというのもある。
縁起恐怖
これも非常に多いもので、簡単なものでは、数にたらわれる。数に好悪があり、三がいいとか四が悪いとか人によって種々な註文がある。三の嫌いな人は、三人集っても不安になり、階段を三歩で上るとまた引き返してやり直すとか、何事にも三を避けるので日常生活に非常な不便を来す。あるいは奇数がいいとか偶数が悪いとかいうのもあり、何かやり始める前に好きなだけの数を数えなければならぬという人もある。またある不善な事件が起った場合、それに関係したあることを非常に嫌うというのもある。例えば怪我をしたとき着ていた着物を二度と見るのも嫌であるとか、その時偶然日曜日だったりすると毎週の日曜が不安になるとか、試験を受けて成績がよくなかった時の登校の通路を嫌うとか、反対にまた、非常に好成績だった場合、その後その時通った路でないと登校が不安になるとか、何でも偶然のことを何か関係があるように感じて恐怖するのである。
尖鋭(せんえい)恐怖
尖ったものを見ると、それが自分を傷つけるような気がして不安になる。針が恐くて裁縫が出来ない婦人もあり、ナイフ、飽丁などのある所では落ちついて仕事も出来ない者、隣家の塀に硝子の破片を植えてあるので引越しをしなければならぬ人、極端なのは、尖った葉の植物を見ても恐怖を感ずる。ある人は寝ているときも、下駄箱の中の鋲のある靴が自分の頭の高さより上にあると眠れない程であった。
高所恐怖
ある学者が調べたところによると、白刃でおどされるときのゾーッとする感じは肩中を肩から下にかけて走り、断崖のふちに立った時のゾーツとする感覚は踵(かかとのこと)の所から足の裏側を沿ってずうっと上に上るものであるという。このように高所において危険を感ずる不快を味うと、その後たいして危険でない高所をも恐れて、そこに行くことが出来ないものがある。あるいは卒倒恐怖の人が、高所で倒れたら大変だというので、高所に行けないものもある。
計算症
目に触れるものをいちいち数えなければ気がすまない。あるいはただ頭の中で絶え間なく数を数えなければならぬという状態で、日常の仕事もそのために支障を来すというのである。
穿鑿症(せんさくしょう)
何の益もないと知りながら何でも穿鑿しなければ気がすまぬ。何故机には足が四本あるか、何故男と女は違うのか、この樹には葉が何枚あるか、東京湾には魚が何匹いるかなどといちいち穿鑿するために毎日ぼんやり暮しているのである。 かかる強迫観念に対する処置は別に他の症状の場合と異なるところはない。彼らは常に気休めことに終始している。安心したい、不安から逃れたいというので、強迫観念を起すまいとして観念を抑圧したり、あるいは観念に従う行動を取って気分を腐らすのである。手を何度も洗った、消毒するとその時だけは気がすむ、同じことを何度も繰返さぬと不安になるので、だらしなく繰返している。苦しいことは避けるという風で、いつまでもどうどう巡りをしている。苦痛不安に耐えて強迫観念はどしどし起しながら、強迫行為を止める、その苦しさを忍んで、なすべき現実の仕事に精進する態度でなければ、新しい境地の打開は望まれないのである。強迫観念は起るに任せ、起しながら実際の仕事をやれるという体験を経て、強迫観念も次第に影をひそめるのである。かくして強迫観念らしき考えが時々頭に閃いても、「おのずから映れば映る、うつるとは月も思わず、水も思わず」という自然の境地も開かれて来るのである。
